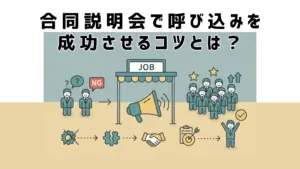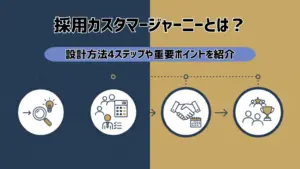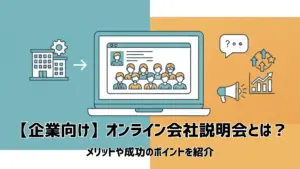採用CXとは?メリットや改善のポイント、事例を紹介
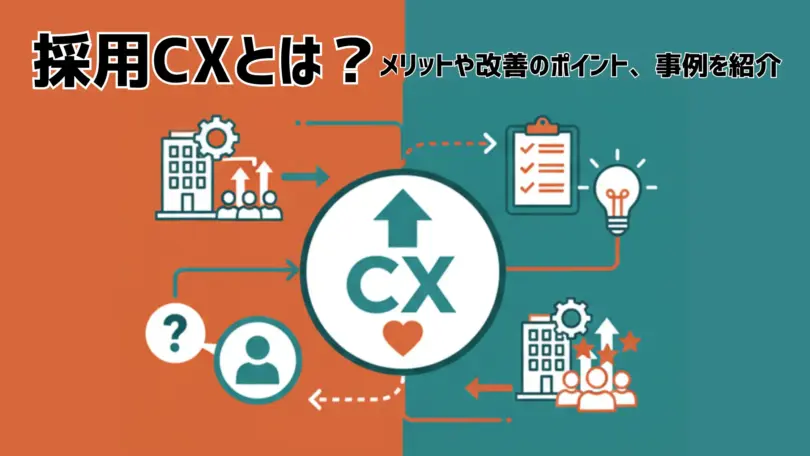
現在、深刻な人材不足やSNSを通じた企業評判の拡散が背景となり、採用CXの質が企業の採用力やブランド力を左右する要素となっています。質の高い採用CXは、優秀な人材の採用成功率や内定受諾率を高めると同時に、企業イメージの向上にも寄与します。
そこで本記事では、採用CXについて、定義や重視される背景、メリット、具体的な4場面の解説、改善するためのポイント、具体的な事例を紹介します。
採用CXとは
採用CXとは、企業の採用活動において候補者が経験する一連の体験を指します。
この場合のCXは、「Candidate Experience(候補者体験)」の略であり、一般的に思い浮かぶ「Customer Experience(顧客体験)」とは異なります。
具体的には、求人情報を見た段階(認知)から応募、選考、内定・入社に至るまで、候補者が感じる印象や満足度、コミュニケーション体験を含みます。この採用CXの質が、候補者にとってその企業の魅力や働きやすさを判断する重要な要素となるのです。
採用CXが重視される背景
採用CXが重視される主な背景は、以下の2つです。
人材の争奪戦が激化しているため
少子高齢化や労働力不足により、優秀な人材をめぐる競争が激しさを増しています。スキルの高い人材は複数の企業からオファーを受けることが多いのが実状です。
そのため企業は候補者に対して、充実した待遇条件だけでなく、応募から入社までの間にも「自社の印象を高める体験」を提供する必要があるのです。
候補者が採用プロセスを通じてポジティブな印象を受けた場合、内定の受諾率や入社後の定着率が高まります。また、採用CXを通じて他社との差別化を図ることが、企業の競争力向上につながります。
SNSなどで企業評判が拡散されやすいため
現代では、SNSや口コミサイトを通じて企業の採用プロセスに関する評判が広まりやすくなっています。良い体験を提供できれば、その評価がポジティブな口コミとして拡散され、企業イメージの向上につながります。
一方で、ネガティブな体験が広まると、評判を落とし、応募者の減少や信頼性の低下を招くリスクがあります。このように、デジタル環境の進化により、採用CXは企業ブランドの向上や信頼構築において非常に重要な要素となっているのです。
採用CXが企業にもたらすメリット
採用CXが企業にもたらすメリットを、3つ紹介します。
優秀な人材の採用成功率の向上
採用CXの改善は、優秀な人材の採用成功率を向上させます。候補者は採用プロセスを通じて企業が重視する価値観や働く環境、従業員への対応などを感じ取り、そこでの体験がポジティブであれば「この会社で働きたい」と思う確率が高まります。
特にスキルや経験が豊富な人材ほど、企業に求める条件が厳しくなる傾向がありますが、丁寧で魅力的な採用体験を提供することで競合他社との差別化が可能です。
以上より、採用活動において良好な体験を提供する企業は、候補者から信頼されやすく、最終的に入社を選んでもらえるケースが増えるのです。
企業イメージ向上とブランディング効果
採用CXを通じて候補者に好印象を与えることは、企業のイメージ向上やブランディングに大きく寄与します。採用プロセスでの対応が誠実で透明性のあるものであれば、候補者はその企業に対してポジティブな印象を抱きます。
そこで抱いた印象は、候補者本人だけでなく、SNSや口コミを通じて周囲にも伝わり、企業の評判や信頼度が高まります。
採用活動の場面は、企業の姿勢や価値観を外部に発信する重要な機会です。そのため、採用CXを重視することは、採用活動だけでなく企業全体のブランド価値を向上させる有効な手段といえるでしょう。
内定辞退率の低減
採用CXが優れている企業では、内定辞退率が低下する傾向があります。候補者が採用プロセスを通じてポジティブな体験を得ると、その企業に対する信頼感や期待が高まり、入社への意欲も強くなります。
一方で、採用過程で不安や不満を感じると、たとえ内定を出されても辞退に至ることが少なくありません。例えば、連絡の遅れや対応の不誠実さは、候補者の意欲を削ぐ原因となります。
採用CXを改善し、候補者が安心して選考に参加できる環境を整えれば、内定後も「ここで働きたい」という思いを維持してもらえます。このように、採用CXは内定辞退のリスクを最小限に抑え、採用の最終成果を向上させる重要な要素です。
採用CXの4場面
採用CXの4場面について、基本的なポイントとあわせて紹介します。
認知
候補者が企業を初めて知る「認知」の場面は、採用CXにおける重要なスタート地点です。「認知」は、以下のような様々な接点を通じて発生します。
- 求人情報:
求人サイトや企業の採用ページに掲載される情報が中心です。ここで候補者が「自分に合っている企業かどうか」を判断するため、職種や条件だけでなく、企業の価値観やカルチャーを伝えることが重要です。 - SNSや広告:
InstagramやLinkedInなどのSNSや、採用関連の広告も候補者に企業を認知させる重要な手段です。これらのプラットフォームでは、視覚的に魅力的なコンテンツが有効です。 - 口コミや評判:
口コミサイトや従業員の評価も、企業を知るきっかけとなります。特に候補者は、企業のリアルな評判を重視する傾向があるため、ここでの印象も大切です。
この「認知」の段階で、候補者が企業に興味を持ち、「応募してみたい」と感じるような魅力をどれだけ提供できるかが鍵となります。
応募
「応募」は、候補者が興味を持ち、実際にアクションを起こす場面です。この場面では、候補者がスムーズかつストレスなく応募手続きに進めることが重要です。「応募」のより具体的な場面は以下の通りです。
- オンライン応募フォーム:
応募プロセスの中心となるのがオンラインフォームです。ここでの手続きが煩雑だと、候補者が途中で離脱してしまう可能性があります。簡潔で直感的な操作が可能な設計が求められます。 - 必要情報の伝達:
応募時に必要な情報を伝える場面です。「履歴書や職務経歴書の提出」「ポートフォリオの添付」などの条件を事前に提示し、候補者に無駄な混乱を与えないようにします。 - 確認連絡:
応募完了後に確認メールを送信することで、候補者に安心感を与えるとともに、今後のプロセスについても明確に伝えることができます。
「応募」の場面は、候補者が企業との関係をより深める第一歩となります。このプロセスでの印象が良ければ、その後の選考への期待感も高まります。
選考
「選考」は、候補者が企業と直接接触し、相互に理解を深める重要な場面です。この場面での体験が、候補者が企業に対して抱く最終的なイメージを大きく左右します。「選考」の具体的な場面は以下の通りです。
- 面接:
候補者と企業のコミュニケーションの中心となるのが面接です。面接官が企業の魅力をしっかり伝え、候補者の話をじっくり聞く姿勢を見せることで、候補者に好印象を与えましょう。 - 試験や課題:
適性検査やスキルテストなども大切な接点です。試験や課題の目的・趣旨を丁寧に伝えることで不安を軽減可能です。 - 各選考ステップの説明:
候補者が次のステップや結果通知のタイミングを把握できるよう、事前にプロセスを説明するのが重要です。不明点が多いと、候補者にストレスを与える原因となります。
「選考」の段階で良い体験を提供することで、候補者が企業に対してポジティブな印象を持ち、内定の受諾率アップにつながります。
内定・入社
「内定・入社」は、採用プロセスの最終段階であり、候補者が企業の一員になるための重要な場面です。この場面での体験は、候補者の入社後の満足度や定着率に大きな影響を与えます。具体的には、以下のような場面が該当します。
- 内定通知:
内定を伝える際には、文書の送付だけではなく、電話やオンライン面談を活用して候補者に直接お祝いの言葉を伝えることで、好印象を与えられます。 - 入社準備のサポート:
入社までの期間に、会社の資料やFAQを提供することで、候補者がスムーズに新しい環境に適応できるようフォローを行います。同期社員との交流イベントも有効です。 - オンボーディング:
入社後の研修やフォローアップが、候補者を職場にスムーズに馴染ませるカギとなります。この段階の体験が良いほど、候補者が長期的に活躍する可能性が高まります。
「内定・入社」の場面では、候補者が企業に対する信頼感をさらに高め、モチベーションを持って新しい環境でのスタートを切れるよう、細やかな対応が求められます。
採用CXを改善するための重要ポイント
採用CXを改善するために特に重要なポイントを、8つ紹介します。
まずは良好な第一印象を得る
採用CXの第一歩は、候補者に良好な第一印象を与えることです。応募者が最初に接する採用ページや求人情報の内容は、企業に対する期待や信頼感を大きく左右します。
情報が分かりやすく整理されており、視覚的にも魅力的なデザインであることが重要です。ターゲット層向けの採用キャッチコピーがあるとより効果的でしょう。
また、候補者が初めて企業とコンタクトを取る際の対応も第一印象に直結します。迅速かつ丁寧な返信や、問い合わせに対する誠実な対応を徹底することで、候補者に「この会社は信頼できる」と感じてもらえるのです。
応募手続きの簡素化と最適化
応募手続きが煩雑で手間がかかると、候補者は途中で離脱してしまう可能性が高まります。そのため、応募フォームは必要最低限の情報を求めるようにし、入力の手間を削減する工夫を取り入れるのが重要です。その際、募集要項も必要な情報を過不足なく掲載し、分かりやすくしましょう。
また、モバイルデバイスからの応募が増加しているため、スマートフォンやタブレットでもストレスなく手続きできる環境整備が求められます。システムの使いやすさや、応募完了後に候補者へ適切なフィードバックを送る仕組みも重要なポイントです。
応募から内定までのスムーズかつ迅速な対応
採用プロセスが長引くと、候補者の興味が薄れたり、他社に流れてしまうリスクがあります。そのため、応募から内定通知までの流れをできるだけスムーズにすることが重要です。
各選考段階でのフィードバックを迅速に行い、候補者がプロセスの進捗状況を把握しやすい環境を整えることが求められます。また、プロセス全体に無駄がないかを見直し、最短かつ最適な流れを構築することで、候補者のストレスを軽減できます。
とりわけ合否連絡の手段や時期の明確な伝達を行うと、候補者は安心して選考に臨むことができ、企業への信頼感も高まるでしょう。
パーソナライズされた親身なコミュニケーション
候補者一人ひとりに合った対応を心がけることも採用CX改善の重要なポイントです。テンプレートのような対応ではなく、可能な範囲で候補者の興味や経歴に応じたメッセージやフィードバックを提供することで、企業への信頼感を高めることができます。
特に、候補者が抱える不安や質問に親身に対応する姿勢を見せることが重要です。企業が候補者を「一人の大切な人材」として丁寧に扱うことで、好印象を与え、内定後のエンゲージメント向上にもつながります。
また、会社説明会時の声かけ、合否連絡時などの場面でのさり気ないコミュニケーションも好印象につながりやすいでしょう。
企業イメージにおける一貫性の担保
採用活動を通じて候補者が受ける印象は、企業イメージそのものに直結します。そのため、採用プロセス全体を通じて企業の価値観やメッセージが一貫して伝わるようにすることが必要です。
例えば、採用ページのトーンやデザイン、面接での応対、内定通知の内容など、あらゆる接点で「この企業らしさ」が感じられる仕組みの構築が求められます。反対に「会社説明会と面接でいっていることが違う」ような状況になると、不信感が一気に募ってしまうため注意しましょう。
面接官トレーニングの実施
面接官の対応は、採用CXにおいて非常に大きな影響を及ぼします。候補者に対して一貫した対応を行うためには、面接官に対するトレーニングが欠かせません。
面接の基本的な進め方だけでなく、候補者の強みを引き出す質問の仕方や、企業の魅力を効果的に伝える方法を教育することで、採用活動全体の質を向上できるのです。
さらに、面接官が候補者に敬意を払い、誠実に接する姿勢を徹底すれば、候補者の信頼感や満足度を高められ、内定受託率アップにもつながります。
候補者視点での採用プロセスの見直し
採用プロセスを改善するためには、候補者視点に立った見直しが必要です。候補者がどの段階で不安やストレスを感じやすいかの把握と、その解消が求められます。
例えば、プロセスが複雑すぎたり、無駄なステップが含まれていたりしないかを検証することが重要です。その際、直近の新入社員にヒアリングを行うのも有効です。
そして採用プロセス全体を通じて候補者が、「この会社で働きたい」と感じられる体験を提供することが重要です。
デジタルツールの活用
採用プロセスの効率化と候補者体験の向上には、デジタルツールの活用も効果的です。オンライン面接やチャットボットを活用すれば、候補者とのコミュニケーションを円滑に進められます。
また、採用管理システム(ATS)や候補者データベースを活用すると、選考プロセスの効率化やパーソナライズされた対応を実現できます。さらに、採用マーケティングツールを活用して、企業の魅力を的確に伝えることも、採用CXの改善に寄与します。
採用CXの事例
採用CXの事例を、3つ紹介します。
応募から入社までのプロセスを意識して採用力を強化
パナソニック株式会社では、採用活動を「認知」「共感」「発掘」「誘引」「採用」「配置」「育成」のプロセスに分け、それに基づいた採用広報の強化を図っています。新卒・キャリア採用を問わず、まずは「認知」を重視した情報を統一的に掲載し、それぞれに特化した情報を個別ページにまとめることで、一貫性のある企業イメージを発信しています。
また、キャリア採用ページ「A Better Career」を通じて、転職希望者やカムバック採用、再就職希望者への情報提供を行い、幅広い求職者に対応。さらに、キャリア登録制度を導入し、求人がない場合でも興味を持った求職者を囲い込む仕組みを構築しています。
このように応募から入社までのプロセス全体を意識した事例は、多くの企業にとって参考になるでしょう。
理念とビジョンへの共感を重視した採用プロセスでマッチ度を向上
株式会社WORK SMILE LABOでは、「いい人材より、(自社に)合う人材」をテーマに掲げ、経営理念やビジョンに共感する人材を採用するプロセスを構築しています。同社は、「『働く』に笑顔を!」という経営理念や「中小企業の笑顔溢れるワークスタイルモデルカンパニーになる」というビジョンを採用活動の中心に据えています。
採用説明会では、待遇や条件、職種といった具体的な情報を敢えて後回しにし、経営理念やビジョンを丁寧に共有することに注力。その結果、理念に共感し、自社と価値観が一致する応募者を集めることに成功しています。
また、採用イベントでは就職活動生に自身のキャリアを考える機会を提供し、入社後も個々のキャリアビジョンを上司や同僚と共有する研修を実施。これにより、学ぶべきスキルが明確になり、社員の学びへの意欲ややりがいの向上、さらに定着率の向上にもつながっています。
理念とビジョンを採用プロセスの軸に据える事例は、企業と求職者のマッチ度を高め、長期的な人材定着に寄与する採用CXの好事例といえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングで高度技術を有した人材を効率的に確保
オムロン株式会社では、中期事業戦略を実行するために、AIやロボティクスといった高度技術を有する人材の採用に注力しています。この分野の人材は市場に限りがあり、通常の求人サービスでは十分な結果が得られないため、ダイレクトリクルーティングを活用して効率的に確保する方法を採用しました。
具体的には、転職潜在層を含む候補者へ直接アプローチできるスカウト機能を活用し、候補者に対して入社への動機づけを行いました。また、新規R&D部門の立ち上げメンバーを採用するため、LinkedInオフィシャルパートナーであるRPO会社と連携し、グローバル規模での人材発掘を実現しました。
その結果、多様性を持ちながらも高度な技術力を有する人材を確保し、技術部門での当事者意識を醸成することに成功。また、広報部門と連携した技術広報活動を通じて、企業の魅力を効果的に発信することで優秀な人材とのつながりを強化しました。これらの取り組みは、採用プロセス全体の効率化と、採用CXの向上に大きく寄与しています。
なお本事例の詳細については、こちらで無料ダウンロード可能ですので、ぜひお受け取りの上、詳細をご確認ください。
オムロン株式会社様の事例 | 株式会社ダイレクトソーシング
まとめ
採用CXとは、企業の採用活動において候補者が経験する一連の体験を指します。
採用CXの改善は、優秀な人材の確保や企業ブランドの強化に直結する重要な取り組みです。採用プロセス全体を通じて候補者にポジティブな体験を提供することは、単なる採用活動にとどまらず、企業全体の信頼性や魅力の向上にもつながります。
求人情報の提示から入社後のフォローアップまで、候補者との接点すべてにおいて、候補者目線での配慮を重ねることで、他社との差別化が可能となるのです。
本記事で紹介したメリットや改善ポイントを参考に、採用CXを見直し、より魅力的な採用活動を目指してみてください。
特に事例でも紹介したダイレクトリクルーティングは、欲しい人材に対して企業から直接アプローチをかけられる企業だけでなく候補者にとっても効率の良い手段です。そのため質の高い採用CXの実現を期待できます。
弊社はダイレクトリクルーティング支援企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いて、自社が求める人材の採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。
最短かつ高いコストパフォーマンスで求める人材を獲得したいとお考えの方は、ぜひ以下の「問い合わせフォーム:無料」から気軽にお問い合わせください。

45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。
関連記事