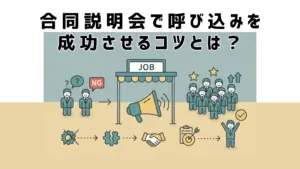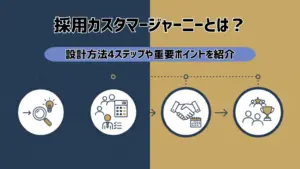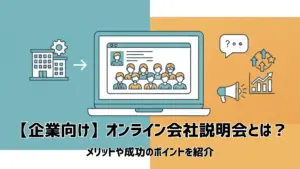採用戦略の設計に役立つフレームワーク8選|効果や活用ポイントも解説

企業の成長を支える人材採用は、計画的かつ戦略的に進めることが重要です。ただし、感覚や経験に頼った採用活動では、思うような成果が出ないこともあります。そこで役立つのが、採用戦略の設計に活用できる「フレームワーク」です。
本記事では、採用戦略を効率的かつ効果的に設計するためのフレームワークを8つ紹介します。自社の採用課題を可視化し、採用活動を最適化するためのヒントを得られる内容ですので、ぜひ参考にしてください。
採用戦略とは
そもそも採用戦略とは、企業が求める人材を効率的に獲得し、組織の成長につなげるための計画や手法のことです。単なる採用活動ではなく、中長期的な視点で人材確保を進めます。
昨今、人材獲得競争が激化する採用市場において、優秀な人材を確保し、組織の持続的な成長を支えるためには不可欠といえるでしょう。
採用戦略にフレームワークを用いる効果
採用戦略にフレームワークを用いることで得られる効果を、3つ紹介します。なお各項目で例として挙げる各フレームワークの詳細は、後の項目で紹介します。
自社の現状や課題を客観的に把握できる
フレームワークを活用することで、自社の採用状況や課題を客観的に把握可能です。
例えば、自他社と採用ターゲットの3視点で分析を行う「3C分析」や、4視点から採用ターゲットのニーズを深掘りする「4C分析」、自社の採用活動における強み・弱みなどを可視化する「SWOT分析」などが挙げられます。
いずれのフレームワークも、自社の現状・課題を客観的に把握し、体系的に整理することで、より有効な採用戦略の立案を実現できるのです。
感覚に頼らない戦略を実現できる
採用活動では、これまでの経験や直感だけで方針を決定しがちですが、フレームワークを活用すればデータに基づいた戦略を立案できます。
例えば、フレームワークを通じて「応募数」「内定承諾率」「採用後の定着率」など採用に関する具体的な数理結果を測定すれば、感覚ではなく根拠のある意思決定が可能になります。
高い客観性に基づいて設計された採用戦略であれば、目標達成の確度は高まります。また、社内の納得や賛同、協力も得やすくなるでしょう。
採用市場の変化に柔軟に対応できる
採用市場は、景気変動やテクノロジーの進化、働き方の多様化などにより、日々変化しています。例えば、政治・経済・社会・技術の視点で環境を分析するフレームワークの「PEST分析」を活用すれば、各外部環境の変化を事前に把握し、採用戦略に反映できます。
採用ブランディングの強化にもつながる
採用戦略にフレームワークを活用すると、企業の魅力を体系的に整理し、採用ブランディングを強化できます。
例えば、ペルソナ分析を行うことで、自社に最適な人材像を明確にし、そのターゲット層に響くメッセージを打ち出せます。
また、カスタマージャーニーマップを活用すれば、求職者が企業を知り、応募し、内定を受諾するまでの流れを可視化し、各段階での接点を最適化できます。これにより、「この企業で働きたい」と思われる魅力的な採用活動を展開できるのです。
採用戦略の設計に役立つフレームワーク8選
採用戦略の設計に役立つフレームワーク8選を紹介します。
3C分析
3C分析は、自社の採用状況や競合環境、市場の求職者ニーズを整理するフレームワークです。企業(Company)、競合(Competitor)、市場・求職者(Customer)の3つの視点から分析することで、戦略的な採用活動を実施できます。
- Company(自社):
自社の強み・弱みを整理し、どのような人材が必要かを明確にする。
例:給与水準、福利厚生、企業文化、キャリアパス、研修制度などの評価 - Competitor(競合):
他社の採用手法や条件を分析し、自社の差別化ポイントを見出す。
例:給与・福利厚生・リモートワークの有無など条件面、活用している求人メディアや採用広告の手法など - Customer(市場・求職者):
求職者のニーズや採用市場の動向を把握し、最適なアプローチを検討する。
例1:業界における有効求人倍率はどの程度か
例2:求職者は安定志向か挑戦志向か、ワークライフバランス重視か
上記のように、3C分析を活用することで自社の採用戦略をより客観的かつ論理的に設計するための土台が整います。
4C分析
4C分析は、採用活動を「企業側の視点」ではなく「求職者の視点」で考えるためのフレームワークです。求職者にとって魅力的な採用プロセスを設計することが可能になります。
- Customer Value(求職者にとっての価値):
求職者が「この企業で働きたい」と感じる魅力を明確にする。
例1:どのような環境・制度が求職者にとって魅力的か?
例2:キャリア成長の機会は十分にあるか? - Cost(求職者の負担):
応募・選考プロセスの手間や転職リスクなど、求職者が感じるコストを考慮する。
例1:選考プロセスが長すぎて負担になっていないか?
例2:応募から面接までのスケジュール調整はスムーズか? - Convenience(利便性):
応募方法、勤務地、働き方(リモート可否など)の利便性を検討する。
例1:オンライン面接の導入で遠方の求職者にも対応する
例2:応募方法を簡単にし、スマホからでもすぐエントリーできるようにする - Communication(コミュニケーション):
求人情報の伝え方や面接時の対応を最適化する。
例1:面接官の対応を統一し、求職者に好印象を与える
例2:内定後のフォローを強化し、入社意欲を高める
このフレームワークを活用することで、求職者の視点に立った採用活動を実現できます。
SWOT分析
SWOT分析は、企業の採用力を強み(S)、弱み(W)、機会(O)、脅威(T)の社内外4つの視点で整理する手法です。
- Strengths(強み):
社内の育成環境、福利厚生、ブランド力など、採用における強みを特定。
例1:充実した教育研修制度
例2:独自の技術による市場ポジションの強さなど - Weaknesses(弱み):
給与水準、知名度、人事リソース不足など、採用活動の課題を洗い出す。
例1:知名度が低く応募者が集まりにくい
例2:給与や待遇が競合より見劣りする - Opportunities(機会):
市場の人材流動性の高まり、DX化による新たな採用手法などの好機を探る。
例1:リモートワークの普及による全国採用の可能性
例2:新卒採用市場の回復による優秀人材の確保 - Threats(脅威):
競争激化、少子高齢化による労働人口減少などのリスクを認識する。
例1:少子高齢化による採用市場の縮小
例2:競合の給与・待遇の向上による応募者流出
これにより、自社の採用戦略を適切に調整し、より効果的な施策を立てることができます。
PEST分析
PEST分析は、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの視点から、採用に影響を与える外部環境を分析する手法です。
- Politics(政治):
政策や国の指針などが採用に与える影響を考慮。
例:労働関連法の改正、外国人雇用政策など - Economy(経済):
採用市場とも関連が深い経済市場を分析。
例:景気動向、賃金相場、求人倍率の変化など - Society(社会):
社会通念の変化やより重視されやすくなった価値観などを考慮。
例:働き方改革、ワークライフバランス、Z世代が重視する価値観など - Technology(技術):
AI・DXの発展による新たな採用手法やスキル要件の変化を分析。
例:AIを活用した採用ツールの進化、リモートワークの普及など
このようにPEST分析を行うことで、社内の将来性を見越した長期的視点での採用戦略を構築できます。
採用ファネル
採用ファネルとは、マーケティングの「セールスファネル」の考え方を応用し、求職者が企業を認知してから入社に至るまでのプロセスを段階的に整理したフレームワークです。
採用活動における各段階を可視化し、どこで応募者が離脱しているのかを分析し、改善につなげることができます。
基本的には、以下の段階に分けられます。
- 認知:
求職者が企業や求人情報を知る段階であり、企業ホームページ、求人広告、SNS、口コミなどが影響する。 - 興味:
求職者が企業に興味を持ち、詳しく調べる段階であり、ビジョンや企業文化、働き方などが求職者の関心を引けるかがポイント。 - 検討:
求職者が応募するか否かを検討する段階であり、具体的な業務内容やキャリアパスなどを提示することで次のステップへの進行を後押しする。 - 応募:
求職者が実際にエントリーを行う段階であり、応募フォームの使いやすさ、スムーズな対応が求められる。 - 選考:
書類選考、面接、適性検査といった候補者を絞る段階ではあるものの、選考辞退を防ぐためには、面接官の対応、フィードバックの質、選考スピードなども必要となる。 - 採用:
内定者が決定して採用に至る段階であり、内定辞退を防ぐために、オファー面談や懇親会など内定者フォローが重要。
このように募集から採用までの各段階を体系的に整理し、それぞれにおける重要ポイントを把握することで採用活動を成功に導きましょう。
ペルソナ分析
採用におけるペルソナ分析とは、企業が求める採用候補者の人物像を具体的に定義したものです。マーケティングで用いられる「ペルソナ」の考え方を採用活動に応用しています。
採用ペルソナは以下の3ステップで設計します。
- 経営層や現場に求める人物像を確認する:
経営層や現場社員に求める人物像を聞き取り、自社として求める人物像を明確化する。 - 収集・整理した情報を用いてペルソナを作成する:
ステップ1で得た情報を整理し、具体的なペルソナを作成する。
例:仮名、年齢、性別、居住地、最終学歴、仕事や企業に求めるもの、キャリア志向、情報収集に用いる媒体など - 作成した採用ペルソナを社内で確認する:
採用ペルソナを作成したら、あらためて社内の関係者と共有して確認を行い、必要に応じて現実的なペルソナに調整する。
TMP設計
TMP(Targeting Messaging Processing)設計とは、採用ターゲットを明確化した上で、ターゲットに刺さるメッセージを作成し、そのメッセージが伝わる採用プロセスを設計することです。
各プロセスの詳細は、以下の通りです。
- Targeting(ターゲティング):
自社が求める人材像を基に、採用ターゲットを明確化する。この際、先述したペルソナ設定を用いるとターゲットを明確化しやすい。 - Messaging(メッセージング):
1で明確化したターゲットに対して効果的なメッセージを作成。自社の強みのうち、ターゲット層への訴求につながりそうな要素を強調し、言語化する。 - Processing(プロセッシング):
2で設定したメッセージを、募集から入社までの採用プロセスでいかに伝えるかを設計する。
例:自社の採用ページに、座談会では採用メッセージを意識した会話を展開するなどを通じて、採用ターゲットにメッセージを実感・体感してもらいます。
TMP設計は、採用メッセージを設定した上で、実際の採用プロセスで実感・体感してもらう点に重きを置いています。
カスタマージャーニー
カスタマージャーニーとは、求職者が企業と接点を持ち、応募・選考を経て入社に至るまでの一連の流れを可視化するフレームワークです。求職者視点でプロセスを整理し、どのタイミングでどのような情報を提供すべきかを設計するのに役立ちます。
以下では、カスタマージャーニーの各段階とそれぞれで活用する施策例を紹介します。
- 認知フェーズ:候補者が会社を知る段階
施策例:webサイトやSNSの活用、求人サイトへの掲載、大学での説明会、キャリアイベントなど - 興味・関心フェーズ:候補者が応募を検討する段階
施策例:求人サイトでの求人情報公開、社員のインタビュー動画、企業文化や業務内容を紹介するブログ記事発信など - 応募・選考フェーズ:候補者が行動を起こす段階
施策例:応募フォームやエントリーの簡潔化、選考スケジュールの迅速な共有など - 内定・入社フェーズ:候補者が最終的に決断する段階
施策例:キャリアプランの明示、入社後におけるサポート体制の紹介など - 継続フェーズ:入社後に定着・活躍する段階
例:オンボーディングプログラムの充実化、定期的な面談やスキルアップ研修など
フレームワークを活用して採用戦略を設計する際のポイント
フレームワークを活用して採用戦略を設計する際のポイントを、5つ紹介します。
複数のフレームワークを組み合わせて活用する
1つのフレームワークだけでは、採用戦略の全体像を捉えきれないことがあります。
例えば、「3C分析」で自社の市場環境を整理し、「SWOT分析」で強み・弱みを明確にすれば、より実践的な戦略を構築可能です。また「ペルソナ設計」と「カスタマージャーニー」の併用によって求める人材の行動パターンを具体化すると、より効果的な採用施策につなげられます。
このように複数のフレームワークを組み合わせることで、昨今の厳しい採用市場に対して、有効な採用戦略を構築することは非常に重要なポイントです。
自社の採用課題に合ったフレームワークを選ぶ
フレームワークは万能ではなく、目的に応じた適切なものを選ぶことが重要です。
例えば、競争環境を把握するなら「3C分析」や「PEST分析」、採用プロセスのボトルネックを特定するなら「採用ファネル」、ターゲットの具体像を描くなら「ペルソナ設計」が適しています。
自社の課題を明確にした上で、最適なフレームワークを選択すれば、より効果的な採用戦略を実現できるでしょう。
フレームワークの作成を目的化しない
フレームワークは採用戦略を設計するための手段であり、作成そのものが目的になってしまっては意味がありません。例えばSWOT分析において、強み・弱み・機会・脅威を洗い出す工程は相応の時間や手間を要し、それ自体も意義深いことではありますが、あくまでもフレームワークの活用は手段であり、目的ではないのです。
少なくともフレームワークの完成にリソースを費やすあまり採用活動の開始が遅れたり、重要な実践部分が疎かになったりしないように留意しましょう。
分析結果を具体的な採用施策に落とし込む
フレームワークを活用して得た分析結果を、実際の採用活動に活かすことが最も重要です。
例えば、「採用ペルソナ」で理想の候補者像を設定したなら、その人物がよく利用するメディアに広告を出す、「SWOT分析」で自社の強みが「働きやすい環境」だと分かれば、それを強調した採用ブランディングを行うなど、具体的なアクションにつなげることが成功の鍵となります。
定期的にフレームワークを活用して戦略を見直す
採用市場は常に変化するため、一度立てた戦略をそのまま維持するのではなく、定期的に見直すことが重要です。
例えば、半年〜1年ごとに「PEST分析」を用いて市場環境を再確認し、「採用ファネル」で歩留まり率をチェックすることで、最新の状況に適応した戦略にブラッシュアップできます。継続的な改善を行うことで、市場に適応した効果的かつ効率的な採用活動を維持しましょう。
まとめ
採用戦略の設計には、客観的な視点を持ち、論理的に意思決定を行うことが不可欠です。そのために、3C分析や4C分析、SWOT分析などのフレームワークを活用すれば、自社の採用課題を明確にし、効果的な採用活動を実現できます。
また、PEST分析などの外部環境分析を取り入れることで、変化の激しい採用市場にも柔軟に対応できるようになります。
各フレームワークの特徴を理解しつつ、活用時のポイントも理解した上で、自社の採用戦略に適したものを選定して用いれば、優秀な人材の確保を実現できるでしょう。
なお弊社はダイレクトリクルーティング支援企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いて、自社が求める人材の採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。
自社にとって最短かつ最適な採用手段を知りたい方は、ぜひ以下の「問い合わせフォーム:無料」から気軽にお問い合わせください。

45分の気軽な相談会を
開催しています

竹村 朋晃
著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)
株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO
▶︎ LinkedInプロフィールを見る
2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。
関連記事